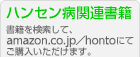出会い(14)チャペカール氏夫妻
 |
| © Jonathan Lloyd-Owen |
チャペカール氏夫妻と初めて出会ったのは、2001年2月の初め、インド南西部マハラシュトラ州の都市プネでした。回復者の組織アイディア・インドのゴパールさんが提唱してきた「ハンセン病回復者自らが発言する会」に共鳴した、社会福祉事業家のS.G.ゴカレ氏が、自分の根拠地のプネ市で会を主催した時、回復者の1人として参加していたのです。いまから思えばこの会はS.G.ゴカレ氏にとっても一つの転換点でもあったと思います。アイディアが出現するまで、ハンセン病に関する集会は、世界のどこを見ても例外なく「関係者の会」であり、良くても「関心をよせる人々の会」であり、「当事者が発言する会」ではありませんでした。たとえ「当事者」が招かれていても、それは主賓でも基調講演者でもなく、参考人に過ぎない程度の立場で、多くの場合、その当事者が「どこの誰さんで、どのような哲学を持って生きる個人か」は問題にされることはなかったのです。S.G.ゴカレ氏は社会福祉の専門家で、国際的にも国内的にも活躍をしている人ですが、ご自分の経歴の出発点がムンバイ北部のハンセン病施設の福祉担当であったことから、ハンセン病は常に氏の意識と活動の一部にあり、長年にわたって回復者とのつながりも続いていたのでした。アイディアの呼びかけはS.G.ゴカレ氏の心のどこかに触れたのでしょう、会の主催を申し出られたのでした。
「発言する会」には約40人の回復者が参加していました。サリー姿の女性や幼い子どもを抱いた若い夫婦もいました。ハンセン病の回復者たちが主要な参加者であるとはいえ、来賓席にならんだ高名な専門医たち―ガナパティ、ピライ、ジャルメータ、ドングレ―を前にして、議論の出来る雰囲気でもなかったのですが、出発点ではありました。この会で印象に残っている人達の中に、チャペカール夫妻とプラカシュ・パティル氏がいました。何分にも地元のマラティ語 ですすめられた会で、ときどきある英語の通訳でかろうじて今何が話されているのか理解できると言う程度でしたので、会の内容は十分に把握できたとは言えません。チャペカール氏と夫人もそれぞれ前にでて話しをされました。お二人はともに上背があり、堂々としていて、人前で話すことに慣れていることを感じさられせました。チャペカール氏は、民族衣装のクルタ(手織り木綿の布地でつくられた一見パジャマのような上着とゆったりしたズボンの組合せ)をまとい、長髪でながい顎鬚をたくわえ、仙人か修行者を思わせる風貌でした。夫人は薄緑色の品のよい色調のサリー姿で、インドの人の中ではどちらかと言えば肌の白い方で、おっとりとしていながら知的な風貌が印象にのこっています。
二日目の夜、S.G.ゴカレ氏夫妻が来賓の数人と一緒に夕食に招待してくれました。その席にチャペカール氏夫妻も招かれていたので、初めて直接話しを聞くことが出来ました。二人とも英語を話し、特にチャペカール氏の方はゆっくりとした口調ですが、話題も豊富な人でした。氏にはさほど顕著な後遺症はありませんが、顔面や両手の指には明らかな障害が残っていました。話しの中で判ったことは、チャペカール氏は大学を終え、結婚もし、仕事にも恵まれていた時にハンセン病を発病し、職もうしなったこと。夫人は夫の発病にともなう数々の困難の中、夫を支えつづけたこと。夫妻はプネ市近郊に自らハンセン病回復者の自立のための小さな施設をつくり、運営していることなどでした。病気になった当人が、施設を開設するとはどういうことなのか、疑問を持ちながらもこの時は十分に理解しないままにおわりました。ただそのときチャペカールさんはこんなことを話してくれたのです。
ハンセン病の診断を受けたころのことでした。いきつけの床屋に行った時、長年顔なじみの床屋の主が、はさみやひげそりなど、自分専用のを持ってきてくれないか、と言ったというのです。つまり商売道具は使いたくない、ということでした。これを聞いたチャペカールさんは、深い屈辱感とともに、生涯床屋にいって髪を切らない、ひげをそらない、と決心したというのでした。
気になっていたチャペカールさんとの再会が叶いました。今年の8月末にムンバイ(旧ボンベイ)を訪れる機会があり、おもい切って車で約3時間半のタレガオンにチャペカールさんを訪ねたのです。かつては郊外の農村地帯であったのでしょうが、プネ市から25キロというこの町は、さまざまな小規模工業や教育施設もできて、あきらかに都市化が進んでいました。チャペカールさんの施設は、町の総合病院に近いかなり広い一角を占めていました。3年半振りにお目にかかった夫妻は思ったより年老いて見えました。以前会ったときの鋭い視線が印象に残っていたので、頭髪もひげもそのまま白さが増したチャペカール氏の年を感じたのでしょう。以前会ったときのことをよく覚えていて、甘いミルク紅茶で歓待してくれました。81才になった本年5月、今まで夫妻で苦労して築いてきた施設の運営をある宗教関連団体にゆだねる決心をし、重責からは解き放たれたものの、精神的支柱として病弱の夫人と共に、施設の一隅の住居で余生をおくることにしたということでした。
ところでチャペカールさんが創設した施設とは、サンスクリット語で"ウドゥヨグ・ダム(仕事の家)"と名づけられた自立のための施設でした。そして茶ペカールさんが自分の生涯をかけて「仕事の家」を生み出すまでには、チャペカールさんにとってある運命的な出会いがあった、ということも今回の訪問で知りました。
アナント・チャペカールさんは1923年3月12日、経済的には恵まれた家庭にうまれました。大学で工学をまなび卒業後はとある企業の技術者の職につき、結婚し幸福な人生が約束されていた34才のとき、ハンセン病の診断を受け、奈落の底に突き落とされたようなショックを受けました。当時この病気は不治とされていたばかりでなく、厳しい偏見をともなう病気でしたから、仕事を続けることは不可能でした。世を捨て療養所で一生隠れ住む人生を前にして絶望感にとらわれていたチャペカールさんの最初の出会いは、ガンジー記念ハンセン病財団の運営する病院 の所長で高名な専門医のワールデカー先生でした。先生は「ハンセン病は他の病気と同様、治る病気だ。隔離の必要はない。」とチャペカール氏に告げたのです。博士の言葉に励まされたチャペカール氏は故郷にもどって在宅で治療を受けました。当時、外見的にはなんの障害もなかった氏は、治療の効果に勇気付けられ、再び社会に復帰し、工科大学で教鞭をとるまでになりました。しかしこの喜びも2年と続きませんでした。病気は再び悪化し、かれはまた故郷に舞い戻ることになったのです。幸い実家は経済的には恵まれており、生活に困ることはありませんでしたが、このままの生活に満足できない氏は、自宅の敷地に小さな作業場を作り、ハンセン病の回復者に職と収入を確保する自立のための施設を始めました。
 |
しかし、この状況も長続きしませんでした。病状が再び悪化し、ついに53才の時の1976年、再度治療を受けるために、このときはプネ市郊外のハンセン病院に入院したのです。自分の人生に光を見出せないまま苦しい日々が続くなかで、チャペカール氏に第2の出会いが訪れました。ある日街の中を歩いているとき、道路ぎわに本や雑誌を並べて売る露店で、一冊の本が目にとまりました。それは「我に手段を与えよ」という題のアメリカ人ヘンリー・ヴィスカルディの著作でした 。その本の表紙はまっ黒の背景に鮮やかにひなげしの花が一輪浮き出したものですが、その花の茎は途中で折れていて、折れた茎を糸で巻きつけて接木がしてあるのです。チャペカール氏はなぜかその本が自分を呼んでいるように感じられたと言います。まさに「目から鱗」とはこのことで、この本はチャペカール氏が思い描いていた、ハンセン病の回復者たちの自立と社会復帰への道筋と重なる思想で、書かれていたものだったのです。
世界に同じ思いの人がいる、実践した人がいる、ということに励まされた茶ペカール氏は自分の土地に、小さな作業場をつくり、ハンセン病の回復者たちに社会に誇れる'職場'と住居を作り出したのです。仕事はチョークや事務用の紙ファイルの製造といった小規模のもので、この他、土地を利用して野菜や果物も生産販売していますす。1985年たったの5人からスタートした「仕事の家」は20年後の今日20人に増え、多くの人々が巣立っても行きました。この間、有志の支援も得て回復者の子どもたちのための寄宿学校も敷地内に建設し、マハラシュトラ州各地から集まった回復者の子どもたち男女併せて50人近くが、小学校の課程を修了するまでここで過ごします。
チヤペカール氏のミッションはこれだけでは終わりませんでした。氏はマハラシュトラ州のをくまなく歩き、各地にばらばらに点在する療養所やハンセン病コロニーを訪ね、それぞれをつなぐことを試みました。回復者の代表としてマハラシュトラ州ハンセン病対策委員会に名を連ねたこともあります。彼の名詞には、州ハンセン病リハビリテーション委員会(元)議長、州ハンセン病委員会(元)委員などの肩書きが見えます。まことに残念ながら、1980年代〜90年代のチヤペカール氏の活動はほとんど外に知られることはありませんでした。彼のネットワークの中にあったはずの数多くの「専門家たち」にとって「当事者の発言」の力を認識するには時が必要だったのでしょうか。
註
- インドは総人口10億人の国です。公用語は18。それに加えて共通語の英語も準公用語ですから、19の言語が憲法で認められています。それ以外に800〜1700の言語があるといわれています。マラティ語人口も約一億人。地方言語の域をこえています。英語が準公用語であるといっても、専門家やかなり高い教育を受けた人とその家族、政府関係者、都市のビジネス関係者等をのぞくと、やはり地元言語の世界です。最大の言語人口はヒンディ語の約40%。
- ガンジー記念ハンセン病財団:1951年R.D.ワルデッカー博士により、インド中西部マハラシュトラ州ワルダ市に設立され、インドにおけるハンセン病対策に優れた業績を残した。調査・教育・治療を組み合わせたSET方式を開発し、当初から隔離ではなく外来治療を基本とした方針で治療行い、同病院で治療をうけた2万人の患者のほとんどは在宅治であった。同財団は数多くの優れた専門医・研究者・教育者を生み出した。
- ヘンリー・ヴィスカルディー:1912年ニューヨークで貧しいイタリア移民の家庭に生まれる。生まれつき腰から下に両脚がない、という重度の障害をもっており、8才まで病院ですごし何度も手術を受けた。
[山口和子(笹川記念保健協力財団)、2009年、原典:「青松」]