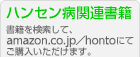出会い(6)真珠湾とカラウパパ
 |
| モロカイ島の街はこの崖の向こう側にあり、街からは見えない場所なのです。ホノルルからカラウパパに向かう定期便の小型飛行機は、一端モロカイ島の飛行場にとまります。ここで大半の人が降ります。その後、島の北に向かい、連なった山なみの東端を廻ると、そこに700メートルの崖の下に小さく舌状に突き出したカラウパパ(半島というには余りにも小さいですが)が見えてきます。「隔離」を象徴する地形に圧倒されました。 |
2001年9月11日、ニューヨークのワールドトレードセンターがテロ攻撃で崩壊した時、アメリカのメディアがこれを1941年の日本海軍によるハワイの真珠湾攻撃になぞらえた事は記憶に新しいことです。この年はまた「真珠湾」からちょうど60年目でした。
ハワイとハンセン病といえば誰もがモロカイ島のカラウパパ療養所を思いだし、同時にこの地で患者救済に尽くし自らもハンセン病を病んで世を去ったダミエン神父の生涯を思い起こします。カラウパパは1866年から1969年までの間に約8000人の人々が、故郷や家族から切り離されてこの地に送られ、この地に生き、そしてこの地の土となったところです。カラウパパに送られるということは、再び生きては帰れないということを意味しており、この地は患者や家族から恐れられていた「隔離の地」であり「墓地」そのものでした。1941年12月7日(日本時間では8日)の真珠湾奇襲は、このカラウパパに大きな転機をもたらしていたのです。当時ハワイでハンセン病と診断された人々はまずオアフ島(ホノルルのある島)のカリヒ病院に収容されました。病状が進行すると、モロカイ島のカラウパパに送られることがありましたが、子どもたちは原則としてカリヒ病院にとどめられ、カラウパパに送られることはありませんでした。カリヒ病院は現在のホノルル空港のすぐ近く、真珠湾から数キロメートルと離れていないところにありました。
6才で家族と切り離されてカリヒ病院に収容されていたバーナード・プニカイアは、その時11才でした。12月7日は澄みわたった空に太陽が輝き「完璧な日」だった、と彼は記憶しています。病院の中庭で14才のキャサリン プアハラと一緒でした。15才のポール原田は、ハウの樹のぼって塀の外を眺めていました。次ぎの瞬間でした。轟音とともに戦闘機が急降下してきたのです。あまりにも低空飛行だったので操縦士の顔や表情もはっきり覚えています。一瞬「訓練?」と思ったその直後、真珠湾は轟音とともに黒煙に包まれ、タッ、タッ、タッ、タッと機銃掃射の音が聞こえ、現実の戦争にみなは震え上がりました。真珠湾攻撃はカリヒ病院の生活を一変させました。カリヒ病院の校舎の屋根には大きな赤十字のマークが書かれており、ここが病院だということを上を飛ぶ飛行機に知らせるようになってはいましたが、いつ攻撃の対象になるかもしれないと夜間の灯火統制やガスマスク着用訓練など、戦争の最前線にあるという緊張の日々が続きました。ほどなく、真珠湾から至近距離のカリヒ病院は爆撃の対象になる可能性があり危険なので、収容者をカラウパパに送るということになり、子どもたちを含め約40人の運命は大きく変わることになりました。
1941年といえば、ハンセン病の治療に転機が訪れつつあるときでした。米国本土ルイジアナ州のカービル療養所では新しい治療薬サルフォンの試用がすでに始まっていました。もし、真珠湾奇襲で急遽カラウパパ送りになることがなかったら、カリヒ病院の人々はホノルルでこの新しい治療を受けることができたかもしれず、カラウパパに送られることはなかったかもしれません。その一方で、もしカラウパパに行くことがなかったら、病気が治って退院することはできたとしても、社会の無理解と根強い偏見にさらされて、困難な人生をたどったかもしれません。いくつかの「もし…」に回答をみつけるのは恐らく困難でしょう。
 |
| カラウパパの墓地 |
1942年5月15日カリヒ病院からカラウパパに向かう40人は、再度の家族との別れに涙にくれて「ハワイ号」に乗りこんだのでした。そして着いたカラウパパの船着場では、当時の400人近い住人たちが、精一杯の晴れ着姿で新しく到着した子どもたちを出迎えたといいます。それまでカラウパパには子どもの姿はほとんど見られなかったのですから、住人たちは率先して子どもたちの親替わりとなり、しつけや教育に努めたといいます。ボーイスカウトやガールスカウト活動、野球チーム、クリスマスなどの年間行事の企画など、それまでとはうってかわって子ども達の声があふれる新しいカラウパパの時代が生まれたのです。1946年にはサルフォン治療も始まり、その後カラウパパへの入所はほとんどなくなりました。1949年から1969年の間に入所した人は32人、全員が本人の希望でカラウパパに転入したとされています。
真珠湾攻撃の結果カラウパパに送られた40人は、カラウパパに新しい時代を築き、みずからもこの地を故郷として生きた人達です。1942年から数えて50年の1992年、移住50周年の記念祭を行い、良き友と良き家族に恵まれ、この地で創造した生活を感謝したといいます。バーナード・プニカイアが、この50年の思いを込めて作詞作曲した美しいハワイアンの唄「カラウパパ・わが故郷」はこの日のハイライトでした。※1
カラウパパ療養所はモロカイ島の北端、標高6〜700メートルの断崖がほとんど垂直に海に落ちるその先端に舌状に伸びる半島の西側にあります。1800年代のなかば、ハワイ諸島に蔓延したハンセン病への危機感から、1865年に「ハンセン病蔓延予防法」が制定されました。続いて時のカメハメハ5世が、島民を感染から守ることを目的に患者の隔離を命じた結果、三方を海に、残る一方は断崖絶壁で囲まれたこの地が隔離の地に選ばれたのです。初期の定着地となったカラワオには豊富な涌き水があったことも一つの要因でした。1866年、最初の船で12人がカラワオ沖に下ろされたときからこの島の歴史が始まりました。※2 それから100年余り後の1969年に、隔離を是認したハワイ州法が廃止されるまでの間に約8000人の人々がこの地に送られました。※3 1800年頃の記録には約1,000人の居住者があったとされています。その中には多様な民族・国籍の人々が混じっていました。ある統計によれば、1908年の住民791人のうち、ハワイ人は693人、中国人42人、ポルトガル人26人、アメリカ人6人、日本人5人、ドイツ人6人、その他13人となっています。カラウパパ療養所に何人の日本人一世あるいは二世が送られたのか、手元に資料がありませんが、ハワイ諸島でのハンセン病蔓延の結果、砂糖黍労働者の移民受け入れが緩和されたとも言われていますから、前記の5人よりは多くの日系人がカラウパパに生きる結果になったことと思われます。
 |
| カラウパパの日系人会のことなどいろいろ話してくれたエド加藤氏(故人) |
私が初めてカラウパパを訪れたのは1996年の5月でした。その当時一世の方は松田治代さんお一人だけでしたが、二世の方は何人も健在でした。なかでも、ライオンズクラブのメンバーであり、画家であり、多彩な芸術家であったエド加藤さんには、昔の日本人会のことなどいろいろ聞くことができました。日本人会がいつ頃できたのか、はっきりした記録はないものの、1933年の集会の記録があり、当時の26条の規約も残っているということです。サルフォン剤以前の療養所では、入所者の寿命も短く、カラウパパに送られて数年の命などと当然のように言われていました。したがって日本人会の主たる目的も日系人同志の助け合い、とくに死後の埋葬の互助が大切な役割の一つであったといいます。会員が亡くなると砂利とセメントを混ぜて墓石を作り、加藤さんたちが亡くなった方の出身地と氏名を刻み込んで墓地に立てたといいます。カラウパパの墓地は舌状の半島の先端部分、海岸の近くにあり、中国人墓地、日本人墓地など大まかな区分けがあります。墓はいずれも西方を頭に埋葬されたのでしょう、墓石は遠く太平洋の彼方の故郷を臨むように並んでいます。しかし、砂利とセメントで作られた墓石は長年の風雨にさらされてほとんど崩れおち、もはや出身地や名前の判読も困難な状況です。しかし中には広島県安芸郡、熊本県菊池郡などと判読できた墓石もあったと記憶しています。
加藤さんの話しによると、戦前のカラウパパ・ストア(日用品を取り揃えた販売部)には沢山の日系人入所者が働いていました。ハーバード早瀬さんがストアの主任、加藤さんが副主任、その他、ハリー山本、ポール原田、シゲミ山下さんなどの名前がありました。早瀬さんとダニー橋本さんはカラウパパ郵便局の仕事もしていたはずです。戦前の日本人会の記録は二人の書記により日本語と英語の両方で書かれていたそうです。太平洋戦争が始まると日本人会の運営もなにかと困難になりました。敵国人視されたり、日本軍のフィリピン侵略のニュースにはフィリピン系の入所者との間に感情的な対立が生まれたりしました。その結果、丁度ケンソー関さんが会長であった時期を最後に日本人会は一時中断します。戦後、名称を「日系アメリカ人博愛協会」と変えて会は復活し、1970年代に解散するまで続きました。
日本人会の楽しみの一つは日本料理でしたが、みなの記憶にあるそれは鶏肉と野菜と昆布の入った「ニシメ」でした。二世の人達の日常語は当然英語でしたが、日本の言葉もそこかしこに残っていたようで、ときには笑い話もありました。あるとき加藤さんは「今日は『ムスメ』だから、来いよ」とある人に声をかけられました。「日本から来たの?」と笑いながら問い返すと相手は怪訝な顔をしています。「ニシメ」のつもりが「ムスメ」と混乱したのです。「ニシメ」といえば日曜日にはよく一世の松田夫人が手料理で日系人仲間をもてなしてくれたことも忘れられないことでした。
「真珠湾」でカラウパパ行きとなったキャサリン・パウハラさんは、日系ではありませんが、日系の人々との楽しい記憶があります。シゲミ山下さんの指導で、女の子たちが12人集まって、桜祭りをしたのです。みんな着物を着て足袋を履き、ピンクの薄紙で作った桜の花で樹を飾り、その下で日本のうたを歌って踊ったというのです。男性たちは「ニシメ」を食べ「サケ」を呑み、ござの上で足がしびれて立てなくなるまで「サクラ」をして遊んだといいます。「サクラ」は花札のことでしょう。
上に名前を挙げた方々のうち、エド加藤さんを始めほとんどの方がすでにこの世を去られました。4「真珠湾」があったためにカラウパパに送られた人たち、とくに年少であった人たちのその後の人生、カラウパパに戦前戦後を通して生きた日系の人たち、隔離の地を故郷にして生きた人たち。全ての人たちの人生を過去のものとして、カラウパパ療養所はその最後の章を迎えています。2003年8月、カラウパパの最後の居住者たちが、自らと数千人の人々の生きた証しのこの地をどのように後世に残して行くのかを話し合う集まりがありました。11才でカラウパパに送られたバーナード プニカイアさんは、現在73才。数回の脳梗塞を乗り越えて、今はホノルルの病院で療養中ですが、8月の集会にはカラウパパに戻って参加しました。人生の最後にはカラウパパの故郷に帰ることを願って、住居はカラウパパにそのまま保存しているということです。
聳え立つ山々 はてしなく ひろがる海
みどり深き渓谷(たに)々々 美しさ充ち満ちるところ
カラウパパ 我が故郷(ふるさと) カラウパパ 我が愛
「カラウパパ・我が故郷(ふるさと)」バーナード・プニカイア 作詞作曲より
註
- 参考:マウイニュース ヴァレリーモンソン記者の記事および「隔離される病」T.ゲーリック/M.ブルームハウス著2000年12月 セパレーティング シックネス基金出版
- カラウパパやダミエン神父については、日本語・英語で幾つかの書物や映画・ビデオなどもあります。
- 送られた人々の記録はハワイ州公文書館他数ヶ所に保管されています。当然非公開ですが、カラウパパ療養所が最終章に近づきつつある現在、最後の住民たちの中で、先人達の歴史を自分たちの手で再確認しようという動きもあります。
- 1996年5月に出会った人々、エド加藤さん、ハーバード早瀬さん、松田さん、ケンソー関さん、ハリー山本さん。みなさん今は亡き人となりました。
[山口和子(笹川記念保健協力財団)、2003年、原典:「青松」]