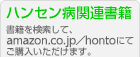真宗(仏教)とハンセン病差別問題について
身分の時代
まず、「らい」とは、歴史的には広く皮膚病が含まれる、人類が最初に認識した感染症ではないかという推測がある。
この病気に対する受け取り方は時代や文化によっても様々である。
日本では、日本書紀・令義解など8、9世紀の頃から記載がある。日本霊異記【註3】下巻20には、法華経を書写していた女の人をそしった罰として「白癩」になるという話が出てくる。これは「法華経・普賢菩薩勧発品」を元とした説話で、後々業病説と言われるように成った所以である。また、ここから「らい者」が法華経に帰依すると病気が治るという逆説的伝説が生まれ、熊本の本妙寺のように「らい部落」が出来る要因になったところでもある。
先の業病という概念であるが、日本では、元々業病説ばかりでは無かったようで「覆載万安方」では主に風病(五大種の内のバランスが崩れること)鎌倉時代の医学書「医談抄」では、天刑病「天の病ましむる病也」とし、律令は解説書である「令集解」では毒虫説としているが、仏教が広まるとことにより「業病」説が定説化していく。
ハンセン病と業の関係では、先の法華経が有名だが、浄土教の聖典である法事讃にも「人中に生じて、聾盲〓〓(おんあ:やまいだれに音、やまいだれに亜)・疥癩癰疽・貧窮下賤にして、」(本願寺出版刊、浄土真宗聖典註釈版七祖篇P544)と業病としてのハンセン病が出てくる。
仲尾俊博師の指摘に、「倫理性の強い因果思想は中国に入って中国の勧善懲悪な儒教倫理に順応して差別を支える」【註4】とあるように、中国に入って為政者の思想である儒教を取り込んだことに問題があるように思える、また日本での佛教は元々為政者のものであったのでこのような儒教的因果論や業は都合が良かったのかも知れない。しかしそのような為政者の論理である業論を点検もせずに用いてきた僧侶の責任である間違いはない。
さて、キリスト教文化圏では、聖書に基づくラザレットという施設が療養所の先駆け的存在であったが、日本では、光明皇后の悲田院や、文殊信仰や地蔵信仰の影響から「救癩事業」は多数見られる。特に叡尊(1201〜1277)や忍性(1217〜1303)の救癩活動が有名で、中には西山光明院のように近代まで続いたものもあるが、残念ながら南北朝以降無くなる。その救癩活動だが、今日考えられるような、治療行為が主な活動ではなく、病人の極楽往生をかなえるために、念仏を称えさせたり臨終行儀のための行為であったとの指摘がある。また日蓮(1222〜1282)は忍性たちの救癩を含めた慈善活動を「聖愚(しょうぐう)問答抄」1265年の中で、偽善的であると言っている。
しかし、社会福祉という言葉もなかった時代、忍性たちの行動は一定の評価出来るものである。
さて、親鸞聖人(1173〜1262)と「らい者」との関わりであるが、歴史的資料としては残っていない。しかし、いくつかの関係は推測出来る。
ひとつは親鸞聖人と善光寺【註5】の関係である。親鸞聖人と善光寺は非常に深い関係があるという五来重師の論がある、善光寺聖としての親鸞聖人像がそれである。善光寺には、「町離」とよばれるエタ身分、「横大門の者」というヒニン身分そして「道近坊」という三種の賤民が在った、「道近坊」には頭がいて、「町離」頭の支配を受けていたようで、この「道近坊」と呼ばれる人たちは「らい者」の集団で、僧体で善光寺境内や町中で勧進(物乞い)や、病人の介抱や死体の処理、田畑の見回りをしていたとされる。このことは田畑の見回り以外は中世の時宗僧や聖たちと同じである。親鸞聖人も聖としてこの集団の中で交流があったはずだ。
次に、親鸞聖人との関係を伺わせるものに、御絵伝に見られる「犬神人(いぬじにん)」を通しての関係である。犬神人(いぬじにん)は元来、神社の下級神職を指す、社の清掃・警固、祭礼の先達、葬送、らい者やヒニンの管理、山門強訴の先兵などと、当時の社会からは考えると非日常的な部分や社会外の部分「ケ」を担わされていた。
この犬神人がなぜ、親鸞聖人の葬送の場に登場するのか。明治三十二年刊の「親鸞聖人四幅御絵傳指南」には、「是なるは犬神人(つるめそう)なり。また夙(しゅく)のものともいふ。(略)祇園會には甲冑を帯して鉾を突出(つきいづ)るなり。今本寺方の葬儀の時にも是の如く。赤き装束に白き頬冠りをして。棒を突きて出る。」とあります。犬神人(いぬじにん)弦召(つるめそ)夙(しゅく)と混乱が起きているが、歴代門主の葬送には犬神人が先達したということが述べてある。例えば、「実如上人闍維中陰録」(真宗資料集成第2巻)「一御葬送御供之次第。一番に棒の衆十人、次に調声鈴の役人、次に御一門衆、次に坊主衆、次に提灯、次に御輿、次に若子・蓑衣の衆悉御供なり。」中の「棒の衆」というのがそれにあたる。また、証如上人の日記【註6】にも度々「弦懸」あるいは「つるかけ」として出てくる。このことについては、これまで犬神人は葬儀の先達が仕事である【註7】と説明されてきたが、河田光夫氏は「本願寺由緒紀」【註8】をあげて、親鸞聖人と「犬神人」との伝承を取り上げられ、親鸞聖人の教化をうけた「弦練作(ツルメソ)」が代々申し渡して、親鸞聖人をはじめ代々門主の葬儀の時に先達をしているのではないかと推測しておられる。
善光寺の道近坊や京の犬神人も、親鸞聖人とのはっきりとした交流は確認されていない、いずれも推測の依稀を出ていないのだが、「れふし、あき人、様々なものは、みな、いし・かはら・つぶてのごとくなるわれらなり」という言葉は、この人々との交流から出たのであろう。
中世から近世にかけてらい者は、先の「道近坊」の他に、「物吉(ものよし)」「オトラシャ」「青癩」と呼称されたグループがある。「物吉」は京都と石川県での呼称で、【註9】京都では、「ものよし」という言祝ぎの言葉をかけながら市内を勧進してまわった門づけの「らい者」集団であった。しかし、京都以外では「物吉」は、らい者を含める場合もあるが、らい者を管理する集団を指す場合がある。また、青癩とは南九州での呼称で京都の物吉と同じような構造であった。
始めに、「らい」という言葉は病名だけの意味ではなく、身分を指す名称ではなかったのかと書いたのはこのような理由からである。感染力が弱いために濃厚皮膚接触した四歳児未満の人しか感染しにくく、潜伏期間が長く発病した時には既に元々の発症者は亡くなっている場合が多い。衛生学という言葉すら無い時代に於いては業病説や家筋(遺伝病説)が出てきても無理もないことである。その結果としてらい者は元々の自分の生活圏を追われたり逃げ出したりして集団で暮らすようになる。この集団が中世・近世には賤民身分として認識され近世に於いては制度として、「らい」という身分が確立していたのだろうと思う。また家筋がさらに偏見を助長し「らい部落」を生み出して行く。実際にはその集落にハンセン病発症者が一人も居なくても、周りから疎外され結婚等の交流がないといった被差別地区が出来ていったようだ。「らい」が被差別身分であるということは、石川県で1871(明治四)年に出た解放令【註10】の中にも見ることができる。
そこには「物吉」も今後同様に一般の民籍へ編入するようにと書いてある、これは「物吉」という集団あってそれが身分として認識されていたということを示すものである。
らい=病気という認識で今まで考えていたのだが、近世以前には、病気という面と被差別身分であったという側面を見落として来たのでは無いかと思う。
[棚原正智(浄土真宗本願寺派光輪寺) 2003年4月27日、原典:「同和教育論究」23号]
真宗(仏教)とハンセン病差別問題について
はじめに
身分の時代
隔離の時代
新たな差別を見据えて
註