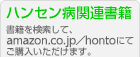インドネシアのハンセン病
 |
2002年の年末から2003年の年始の約1週間、インドネシア、スラバヤの大学病院皮膚科で、ハンセン病外来を見学する機会を得ました。そこでの体験を紹介します。
日本国際協力事業団(JICA)の「シニア海外ボランティア」として、スラバヤで仕事をしておいでの和泉眞藏先生に案内して頂きました。和泉先生は、長年日本でハンセン病の治療と研究に携わっていた方です。普段はJICAの援助で建てられた熱帯医学研究所Tropical Disease Center (TDC)で仕事をなさっていますが、私の滞在期間は、午前中、Airlangga(アイルランガ)大学病院皮膚科外来の見学におつきあいして頂きました。病院内部は、和泉先生と懇意にしているIndoropo (インドロポ)先生にご紹介して頂きました。この時インドロポ先生は、アイルランガ大学の皮膚科講師でした。ハンセン病が専門で50代くらい、180センチはありそうな、インドネシア人にしては大きい方です。昨年、脳出血のため、左半身麻痺となったにもかかわらず、かなり精力的に活動しておいでです。午前は大学、午後はTDC、夜は、自分の診療所で働きます。インドネシアでは、大学病院の給料が著しく安いため、大学に勤務しつつ、自分の診療所を持っている医師が多いそうです。
インドネシアについて
広さは日本の5倍。世界でいちばんイスラム教徒の多い国です。1600年ごろからオランダの植民地支配を受け、太平洋戦争では日本が占領しました。戦後独立しましたが、今も反政府運動などが散発して混乱が続いています。人口は約2億で、世界で4番目に多い国です。
スラバヤについて
インドネシアで一番人口の多いジャワ島の東に位置し、首都ジャカルタに次ぐ第2の都市。南緯7度、平均気温約30度
アイルランガ大学の皮膚科外来で
オランダ統治の名残なのか、スラバヤの市内には、オレンジ色の瓦屋根と白い壁の建物をたくさんみかけます。この大学も例にもれず、石造りの古い建物です。高い天井の続く長い廊下を歩いて皮膚科の外来にたどり着きます。迷子になりそう。皮膚科の外来は、アレルギー、美容、性病、などにパーテイションで区切られていて、ハンセン病外来はその一角。外来患者のなんと、10〜20%がハンセン病患者です。ハンセン病患者は、市町村での保健活動でほとんどが加療され、そこで治りにくかったり問題が生じたりした患者さんだけが、東ジャワ州領域の基幹病院であるこの病院にくるわけなので、ハンセン病の数が多いこと、よくある病気であることが分かっていただけるかと思います。日本ではハンセン病の患者さんは学会で時々報告されるだけですから、驚きです。
いくつか気づいた点を挙げます。
経済的なこと
日本では意識しない、経済的なことと、そこから生じる問題を考えさせられました。
DDS,リファンピシン,クロファジミンの多剤併用療法(MDT)を開始後、DDSとリファンピシンに対して、アレルギー反応がでるから、とクロファジミンのみ投与されている患者さんに会いました(治療と薬の詳細は別の項参照)。この患者さんは、らい菌に対する免疫がなく、菌をたくさん有するタイプ(LL型)。本当はオフロキサシン、ミノマイシンを追加した処方を実施したいのですが、本人に経済的な余裕が無く、投与できません。MDTは患者さんにとっては、“ただ”ですが、他の薬は自費。日本ではそんなに高価とは思われない薬でも、この国では払えない人が多いのです。ハンセン病は感染症で、その患者さんが治らなければ、そこから菌がまた広がるわけで、その患者だけの問題ではない、ということに皆がきづいて、サポートする体制が出来てこそ、ハンセン病の根絶への道が開けると思います。
病棟にいるハンセン病以外の患者さんも見せてもらいました。日本でしょっちゅう使用されている免疫抑制剤、ビタミンD3軟膏などの薬が、価格のために選択肢にも入っていなかったり、逆に日本では副作用の発現率が高くて、あまり使用されない薬が使われていたりしていしました。
文化的なこと
これは、たまたま、ここの外来だけがそうなのかもしれませんが、どうも、医師が自分で処置をしないようなのです。患者さんの菌検査(皮膚に小さな傷をつけて組織を採取し、その中の菌の数を顕微鏡で調べます)、採血、包帯を巻くことなどすべて技師さんがするのです。発展途上国では往々にして、メイドがいる、運転手がいる、といったような、身分によって仕事をわけるような傾向をみますが、その延長でしょうか?医師はその手技が出来てしないのなら、効率向上のためと解釈しますが、本当にできるのか、ちょっとあやしげ…。菌検査を判断するのも技師。でも、その判断に使われる顕微鏡は、30年もたっているような、視野がセピア色の年代物…。
和泉先生は、菌検査をご自身でやりなおして、技師さんが陰性と報告していたものの中に、菌がいたことを実際に示し、現在のやり方ではまずいのではないか?と助言していました。
プレドニン依存症の問題点
(少し専門的なお話です)
さて、大学病院という特殊性もあってか、らい反応(治療の過程や病気の過程で急激に起こる強い炎症反応)を繰り返し、プレドニン(副腎皮質ホルモン剤の1つで、炎症を押さえる作用がある)依存になっている例がとても多かったように思います。らい反応には1型と2型があり、1型の治療にはプレドニン、2型の治療にはプレドニン、サリドマイド、クロファジミンがよく使われますが、このプレドニンの長期投与による、ムーンフェイス(プレドニン等副腎皮質ホルモン剤の副作用で、顔がお月さまのように膨れること。満月様顔貌)を、よく見かけました。プレドニンは、炎症による痛みや熱をよく抑えてくれますが、プレドニンを内服していないと症状が出てきてしまうため、中止できない患者さんが多いのです(これをプレドニン依存症とよびます)。プレドニンの長期投与が続くと、ムーンフェイスを始めとして、免疫低下、糖尿病、骨粗しょう症など、様々な副作用が起こって来ることがあります。
このようならい反応におけるプレドニン依存症の患者さんに対して、サリドマイドを使うのはどうだろう?と和泉先生は、数人の患者さんに投与を始めたところです。
数日前からサリドマイドの投与を始めた患者さんが、TDCに来ました。ある患者さんは、3年も続けていたプレドニンを減らすことができて、喜んでいました。インドネシアをはじめ諸外国では、往々にしてサリドマイドの使用が禁じられています。患者が誰かに薬をあげてしまい、どこか未知のところで副作用が発現してしまうかもしれないからと聞きました。サリドマイドは、確かに妊娠しやすい時期に投与すれば、奇形児が生まれるという重大な副作用がありますが、適応を誤らなければ、安価でよいお薬です。そこで、和泉先生は、まず治験として、投与を開始するプロジェクトを始めました。
サリドマイドをステロイドの替わりに使う治験を始めようというのは、画期的なことです。ステロイドの投与をやめられなくて入院していた30代の患者さんが、敗血症(細菌が血液中で爆発的に増える病気。)で亡くなったことを日本に帰ってから聞いた時、特にそう思いました。勿論、日本でなら回復可能な敗血症だったかもしれません。
その他
MDTがおわって7カ月目に皮疹が再燃した患者をみました。らい反応を伴っているようですが、菌の数も増えています。しかしハンセン病を担当している大学病院の医師は、MDTを再開しようとせず、らい反応に対するプレドニンの投与だけ。MI (morphological index; 菌の形態によって活動性を評価する)が上がっていないから菌の活性がない、と言っていましたが、プレドニンだけ投与したら、免疫を抑制し菌を増やす方に働いてしまうのではないでしょうか…。これはちょっと乱暴な治療。案の定、和泉先生がスメアをとったら陽性で、MDTを再度行う必要ありということになりました。このような症例が何例かありました。MDT後のフォローアップも大切です。現在使われているMDTのプロトコールのように、1年で投与期間が十分か?という問題をあらためて実感しました。
日本人医師の働き
このように和泉先生は、現地医療スタッフの指導、臨床およびPCR等の先端技術の指導、MDTのプロトコールの見直し、サリドマイドの導入など、多方面で活躍しています。
TDCでの仕事の見学もさせて頂きました。ここでの仕事は、主に検査、実験です。PCRという技術でのハンセン病の診断、耐性菌を診断することなどが目標です。和泉先生は、昼食をとる前に必ず、菌検査した標本の染色とか何か、実験を少しやります。ある日、インドロポ先生が、まずご飯にしよう!おなかが空いたと言っているのに、和泉先生が、《患者が一番、実験が2番、食事はその後!》といっていたのを聞いて、それぞれの国民性を象徴しているなーと思いました。
最後に
インドロポ先生に、日本にはハンセン病の患者がほとんどいないのに、なぜあなたは、勉強するのかときかれ、返答に詰まりました。国際医療協力に興味があって、皮膚科の分野で、代表的なものはハンセン病だから、と思っていたけれど、なぜあえて、日本で身近にある病気でなく、ハンセン病なのか?現地の人に任せておけばいいのではないのか?
実は私がインドネシアに行く前の2002年10月に、バリ島で、たくさん死傷者を出したイスラム過激派組織による爆発事件があったばかりで、少し怖かったのですが、色々考えているうち、イスラム過激派の人々の心を動かすのは、武力ではなく、人道的支援等に代表される“愛の力”ではないかと思いました。何が出来るのか分からないけれど、まず、行かなくては、という気持ちで出発。いざ、インドネシアに行ってみると、ハンセン病のことは、より多くの患者と接する現地の専門家に勝ることはできないかもしれない、と思いました。今、私に何ができるか?少し悩みました。そして、私の視点で経験したこと、見たことを知らせることではないかなと思いました。少しでも多くの人に、身近な問題として、発展途上国で起こっていることを知ってもらえたら、何かが変わるのではないでしょうか?世界の平和を祈って。
[間山真美子(三沢市立三沢病院皮膚科) 2003年5月15日]