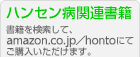金新芽講演会「石ころの叫び」講演録
2005.5.22、早稲田大学にて
心を通わせることの喜び
 |
| 講演する金新芽さん © Mogi Ryo 2005 |
この年老いた身でここに来るというのは、私にとって、なかなか想像ができないことです。私が日本に来たのはこれで5回目ですけど、14歳の時に、修学旅行で九州に来たことがあります。また、18歳の時に修学旅行で東京まで来ました。そして、1980年にはFIWCの招待で夫婦そろって、熊本まで行きましたけど、その後、1990年に立教大学の学生で野渡さんと足立さんという2人の学生のボランティア活動を通してもらった奨学金によって私を立教大学に招待してくれて講演をしたことがあります。
それで私の日本行きは終わるのかと思いましたけれども、また、今回、日本に来ることができました。80年に来た時には食べ物が口に合わないことに苦労しました。90年の時には、朝起きた時に喉が詰まってしまって講演をするのに苦労をしたという経験をしたため、「今度、日本に行く時には声が詰まらないにしてください、食べ物が食べられるようにしてください」と、神様に祈りながらやって来ました。それがかなったせいか、来てみると食べ物が美味しいんですね。それから、ご覧の通り、お聞きの通り声が詰まっていないんです。風邪のせいか少し声がおかしいのですけれども、なるべくきれいな声でお話を進めてみるようにしたいと思います。日本に来たら新聞社の皆さんも来てくださって、果たして私がこのような所で講演をする資格があるのかどうか自分に尋ねてもおりますが、しかし、一旦、講演をするようにまかせてくださった皆さんの好意に対して、最善を尽くそうと思っています。
ここでお話が変わるのですが、司会をしている松長さんは私に比べて相当に背が高いでしょう。昔、少年の時に、少年倶楽部だったら少年キングだったか、ある漫画が思い出されます。一人は背が高いんですね。一人は小さいんです。それで背が大きい人が小さい友達をからかうんですよ。なんか、一寸法師だとか何とか言ってね。ある日、その小さい方の友達が高い友達の所に遊びに行くんです。しかし、たまたまその友達がいなかった。それで見渡してみたら洋服かけにズボンがかかっているんです。自分でも履けるようなズボンなんです。一寸法師とからかっているけれども、自分が履いているズボンもそう長くないんだなと思って履いてみたら、それがちょうど合うんですね。そうしたら、ちょうどその時、その友達が帰って来たんです。それで背の低い友達が高い友達に向かって「おまえ、僕のことを一寸法師とからかっているけれども、君のズボンは僕にぴったり合うじゃないか」と言いました。すると、背の高い友達が非常に驚いて、「あぁ、君、それは半ズボンだよ。」
そういう漫画があって、松長さんと私とのつりあいが少し合わないような気もしますが、まぁ、少々、ご了承ください。ある面では、若い松長さんと80歳の私とは、ある面では平衡が取れないのではないかと思うのですが、ある面で2、3回会いましたけれども、心が合う面があるんですね。年齢とか民族とか女性とか男性とか、そういうものを超えてお互いに繋がるものがあるのです。やっばり、重要なところはそれでしょう。
森元さんとか菊池さんとか。ここに来ておられる柳川さんとは30年来の友達ですけれども、若い友達ですね。それから、土曜日の夜には、いつも日本にいる皆さん方を名前を挙げながら祈っているのです。それは100名くらいでしょう。私が30年くらいの間、FIWCの人たちと交わって、本当に多くの日本の方々と会いました。その人たちの名前を全部覚えることはできないのですが、とにかく、覚えるだけ覚えてみるのです。ですから、市川喜代子さん、足立陽子さん、川合麻子さん、藤本謙一さんとかね、楠原理恵子さんとか。北の方からずうっと沖縄の方に行って、藤岡さん、その夫の大場さんとか。そういう人、一人一人の名前を呼びながら、「神様の腕(かいな)で抱いてください」というような祈りで終わるのですが、そういう皆さんとの関係というのが、私としては非常にいいのです。本当に良い友達をたくさん持っているなと思います。そういう楽しさがあるのです。とにかく、そういう長い間の皆さんとの交流との中で、いろいろな出来事などがありました。今日は「石ころの叫び」という題目ですから、私の80年の人生を断片的にお話してあげたいと思っています。
忘れられない親孝行
幼い時のことを、あまり硬くなく、柔らかい容易な話し方でお話をしたいと思います。
13歳の時ですから小学校6年生でした。今でも覚えていますけれども、ヤマモト・シズオ先生という、あご髭が黒い先生がいました。その時、日本の教科書の中に乃木大将のお母さんの話が出てきました。その乃木大将のお母さんが非常に厳格で、乃木大将を立派に育てたという話でしたけれども、その本をずっと勉強していた時、先生は「乃木さんのお母さんは偉いでしょう」と言われました。そして、「皆さんの中でも乃木大将のように偉いお母さんはいますか?」と言うんです。とっさの質問に皆、黙っていました。50名くらいの学生がいて、その中には10何年もの大学の学長を勤めていた大学教授の友達もいましたけれども、誰も手を挙げないのですね。その時、私は瞬間的にこういう考えが浮かびました。「乃木大将のお母さんは乃木大将にとっては世界で一番立派なお母さんだったのだろう。しかし、私にとって、私のお母さんは世界で一番立派なお母さんじゃないか」と。それで、その時、私は一番前の席に座っていましたけども勇敢に手を挙げました。他に誰も手を挙げた人はいませんでした。先生は尋ねました。「あぁ、金君、君はどういうお母さんを持っているか?」
それで、今、考えても、そういう答えをどうしてできたのかと思いますが、6年生くらいですから、少しは日本語がしゃべれるんです。私は「乃木大将のお母さんは乃木大将にとっては世界一だけど、私のお母さんは私にとっては世界一です。」と答えました。その時、先生の瞼に潤いが見えました。涙がありました。感動的な何かを与えたようでした。
私はその後、22歳の時に家を出て、今まで60年ですね。家を離れて、その間にお父さんもお母さんも死んだのですけれども、60年前に家を出てから、一度として家に正式に帰れない。ですから、お父さん、お母さんの誕生日も一回もお祝いができなかったのです。しかし、私はそれにしても、あの時、私は50名もいる子供たちの中で、私のお母さんの事を皆の前で誇ったという、その事が、私は一回も孝行ができなかったんですけれども、その時にそのように皆の前で答えることができたという一つの孝行が、私の全ての不幸を補っているんじゃないかと思っています。それは50名だったんだけれども、それが500名であっても、5万名の前であっても、私は手を挙げて、私の母のことを誇ったことでしょう。だから、その一度の孝行が何回も誕生日のお祝いをしてあげたことよりも勝るとも劣らない出来事だったのではないかと、私は自分の心を慰めましたけれども、その先生は、その後、日本に帰って神主をして生きられたということを聞きましたが、その後も私をかわいがってくださいました。もちろん、私はお母さんの話をしようと思っているのではないのですが、私の幼い時の出来事として、それがなかなか忘れられない話なのです。
FIWCとの出会い
22歳の時に私は家を出ました。小さい時に病気に罹ったらしいのですね。それが正式に診断を受けないまま、そのまま中学校に通って学校を卒業して社会に出て行って、それから、すぐ病気のため社会から追われて家で隠れていたのですけど、21歳の時、8月15日、戦争が終わったというあのラジオ放送を聞きました。それはまさに夢のような話でした。朝、今日、正午に重大放送がありますと言ってました。ソ連が何日か前に友好条約を破って越境して関東軍を攻撃して来たでしょう。皆さん方、歴史の中でわかっていらっしゃると思いますけれども。ところが、あの宣戦布告をして来たのに日本は黙っていたのです。だから、今日、ソ連に向かって何か宣戦布告をするんじゃないかと思いましたけれども、正午にラジオをつけてみたら、ヒロヒトさんの歴史的な話が流れて来ました。ところが、それまで私たちは自分たち韓国の旗をわからなかったのです。太極旗というのですが。どういう旗が私たちの国旗かわからなかったのです。日本の総督府はその旗を一切見せてくれないのです。ところが、12時が過ぎたら、いつのまにか、その旗がプサンの市内で全部掲げているのですよ。皆々が、どこからその旗が出てきたかというくらいに。その旗を手にしながら万歳を叫びました。私は屋上に上がって、その万歳の群れを見ながら、新しい時代は来たけれども、私はあの波の中に同族として入って行くことができない、自分は落伍者として社会から遠く下がっているという自分自身の姿に非常な悲しみを覚えました。
その年に私は病院に入って、そこで60年の間ずっと住んでいました。その間には、いろいろな話がありますけれども、一番、重要な出来事がFIWCとの出会いです。それが私の生涯の中で一つの重要な出来事でした。私は54歳の時に小鹿島(ソロクト)に渡りましたけれども、たまたま、ある村の人々が「私たちで村を作ろうとしたが、なかなかうまくできないから一つ助けてくれないか」と言いました。しかし、私もよく目も見えないし金もない。私にできることがないのです。だから、他の人を送ってあげたのですが、皆が「そこは駄目だ。希望がない村だ」という。しかし、あまりにその村の人たちが私の所に来て、願うので、その人たちの熱意に負けて、自分は教会を建てて、教会を中心とした一つの村を作ってみようという、そういう考えで、家内を連れてその村に行きました。しかし、そこは何もない荒野のような所でしたけども。そこで自分は他の定着村や教会などを回りながら献金をもらって、それで30坪くらいの教会を建て、とにかく人々を集めて村を作り始めました。それが今は相当に大きな畜産の村として育てられていますけども、それは自分としてはできない作業ですね。
しかし、その時に来てくれたのがFIWCのメンバーだったのです。神様は本当に必要な時に彼らを私の村によこしてくれて、それから1年に一回、15、6日くらいワークキャンプをして、韓国の大学生と日本の若い人たちが来て仕事をしてくれたりして、それが私たちの村だけではなく国内にあるいろいろな定着村に行って労働奉仕をしたり小鹿島にも行ったりしましたけれども、それがずっと今まで30年くらい続いているのです。だから、それが15日くらいだったら、あまり大きな仕事はできないのですけれども、彼らの労働奉仕が私の村や他の村に非常な影響を与えているのです。例えば、彼らが来る前までは、周辺から「乞食の村」と呼ばれたりして、なかなか近付かないしね。しかし、彼らが来始めてからは、地域社会の人たちの見方が違って来ました。それまで彼らはなかなか近付かなかったのです、子供たちも学校に行きずらかったのです。受け入れられなかった。しかし、FIWCの若い人たちが来て、そこで仕事をし始めたら、町や近くの村の人たちが非常に驚異の目で見始めたのですね。だから、教育監や郡守さんなども来て、また、近くの教会や村の長も来て、お見舞いをしたり。ある時、私はオルガンを聴きながら、荒城の月を歌ったりもしましたけども。それで、だんだん変わって行くのが、やはり若い日本の人たち、韓国の若い大学生が来て、一緒に生活を共にするという、そういう面を見て、地域社会の人たちの考えが変わって来ました。
ですから、道を作るということも大切ですけれども、そういう目に見える結果よりも、見えない面のそういう啓蒙とか精神的な地域社会の変化が大切だと思います。それから私たちの村の子供たちも学校に入れることができました。スムースに学校に入れられるようになって、だから、今は非常に変わってきましたね。今は鶏が50万匹、豚が2万頭、子供たちを合わせて150くらいの家族です。おもしろいのは、一つのキリスト教の教会共同体というのは、やはりそういうものなのですね。皆々が信仰をもって、皆々が一緒に畜産組合を作って生活をしている。松長さんも来ましたし森元さんも来ましたけど。とにかく、30年前とは全然違っています。子供たちは大部分が大学まで行くのです。
定着村の人たちの生き方
今日、共同通信の記者から、「日本の隔離政策をどう見ていますか?」と聞かれましたけれども、私の次のように言いました。日本の隔離政策のために犠牲とされた人々は、補償金をもらって社会に復帰したとしても、彼らの老後を見守ってくれる子供たちがいない。しかし、韓国の定着村の人たちは皆が子供を持っているのです。今では会社員になったりお医者さんになったり学校の先生になったりしている人がたくさんいます。日本のハンセン病の政策は韓国よりも相当に、さっき、キリスト教の団体で好善社という、140年の歴史を持った団体の話を聞きましたけれども、小鹿島は歴史が89年です。だから、宣教師たちが来たのはそれより5、6年前ですが、それでも50年くらいその韓国の方は遅いのですね。しかし、ある面では、韓国のハンセン病も同じ時期に終わりに来ているのではないかと思っているのです。それが、日本の隔離政策と韓国の定着村を作りながら進めて来た政策との非常に比較できる問題ではないかと思います。
私は80年に日本に来た時に、ある方から「韓国の皆さんの中にも文学がありますか?」と聞かれて、私は少し躊躇しました。それで、このように答えました。
「そうですね。韓国でも私たちの療友の中でも韓何雲(ハン・ナウン)という有名な詩人がいましたけれども、もう亡くなっています。しかし、韓国では日本の療養所とは違って、日本では皆さんは文字で文学を書くようですが、韓国の定着村の人たちは文字で書く文学ではなく、体で書く文学をやっています。」と答えました。
それで私は、その説明をしました。定着村の人たちは朝早く起きて、鳥小屋や豚小屋に入るのです。そこで一日中熱心に働き、自活しながら生活をしています。その一方で子供たちの勉強もさせているのです。それで大部分の子供が学校に通うことができ、また、大学にも通わせているのです。私は彼ら大学生が20名、30名が日曜日に教会に来て合唱をする場面を聞きながら、彼らが立派にすくすくと育ったその姿を瞼に描きながら考えました。あの子らは定着村の人たちの芸術だ。体で書いた芸術であり、文学であるんだとね。
ですから、そういう面でも少しだけ日本とは違うのですけれども、だから、これが良いとか悪いというような問題ではなく、両国では違う生活をしているのですが、やはり、さっき森元さんも言いましたけれども、補償問題で、長い間、一生懸命に戦って、日本の皆さんの権利のために戦った事件などは、私たちにはなかなか考えられない立派な生き方、戦い方、人生の戦い方ではないかと考えています。そのおかげで、韓国でも個人的に9名の老人たち、もともと日本の療養所にいた人たちで韓国に帰って来ている人たちを9名探し、また、その家族たちを探して3年くらいの間に日本のお金で1億700万円くらい、韓国のお金で10億7千万ウォン手渡せてあげられているのです。今は日本の弁護士さんたちか来て、小鹿島の100名くらい、昔、小鹿島にいた人たちの補償問題で、本当に苦労しているのですが、とにかく、そういう面で日本の療友たちの戦いは韓国の療友たちには真似ができない立派な生き方なのではないかと思います。
「石ころの叫び」を執筆して
私がその後で本を書き始めたのが75歳の時でしたけれども、生涯で最後に何をするかということを祈り始めた時、自分の本を書き始めることがその使命ではないか、クリスチャンとして自分がいただいた神様の恵みを多くの人たちに証しをするということは自分の使命ではないかと思い書き始めました。実際、書き始めてみると、それはなかなか難しいことでしたが、しかし、それは自分の最後の仕事だと思って、熱心に祈りながら書き、また祈りながら書き、私自身の生涯を書いてみて考えたのが、「あぁ、私の人生とは、まさに石ころのような人生だったな」ということでした。小さい時から民族的にさいなまれ、また、病気にさいなまれ、貧しさにもさいなまれ、戦争にもさいなまれ、病気で人々から蹴られ、投げられ、石ころのように踏まれて来た私自身の生涯は、まさに石ころのような人生でした。軍靴も踏んで行く、草鞋も踏んで行く、下駄も踏んで行く、牛や犬も私の顔に、石ころの上に糞をかぶせる。それから、重い荷を積んだの車も私という石ころの上を通るのですけど、そのように押されながら、踏まれながらの80年の生涯だったということを考えました。
聖書のルカによる福音書の19章40節に、キリストがおっしゃったことがあります。キリストがエルサレムに平和の王として入城する時に、エルサレムの市民たちが「ホザナ!」と叫ぶ。それは「私たちを救ってください」という万歳の喚声だったのですけれども、とにかく叫ぶのです。そうしたら、パリサイ派の人たちが「その叫びを黙らせてくれないか」と言うのです。そうしたら、キリストが「彼らが黙れば、道の石ころが叫ぶだろう」と言いました。その時、私はその道の石ころとは何を意味するのかわからなかったのですが、私の生涯をずっと書き始めてから、その石ころの意味がわかって来たのです。それは世の中から忘れられ、軽んじられ、捨てられた、そういう人たちの痛みが避けられない、自分自身の権利を求められない、そういう世の中、一番下の下に存在する人たちを指して言われた言葉だということがわかって来ました。
私は島崎藤村の「破戒」という本を読みました。その本は部落民のことを取り上げているでしょう。皆さんの中でまだ読んだことがないという人がいれば、ぜひ、読んでいただきたいと思います。部落民は自分の素性を明かすことができなかったので、それを明かせば結婚ができないし、そこから追われる。そこで、自分たちは部落民であると絶対に知られてはいけないという戒めをしたでしょう。破戒の主人公が結局、その戒めを破りながら、「自分は部落民です」と叫びながら自分の正体を明かすという本ですけれども、ある意味では、その部落民よりも韓国の私たちの療友たち、同じ境遇にいる人たちは、病気が治ったとか、大学の教授にもなったり、社会の中で生活しているのですけれども、皆々、自分たちの素性を明らかにすることができないのです。自分がどこの生まれであるとか、自分のお父さんがどういう人であるとか、絶対にそれを表わせない。もし、そういう病歴を持った人の息子である、娘であるということがわかれば結婚話が全部壊れてしまうというというそういう状態ですよ。結局、自分の素性を表わすことができない、あからさまにすることができない人、それは罪人でも前科者ものでもないのです。しかし、私の生涯を振り返ってみて、まだまだそういう偏見の中にあるということを考えると、まだまだ私たちは石ころのような存在だなということを考えまして、結局、私の本の題名を「石ころの叫び」としたのです。
弱さを負う人たちと共に生きる
しかし、私はこの「石ころの叫び」という題名は、決して不平と不満とか、政治的な戦いの意味での叫びではないのです。このあいだ、労働者たちのデモでこの言葉が出て来ましたよ。石ころの叫びという言葉。あのキリストの話を知っているのかなと思いましたけれども、しかし、その意味は政治的な闘争としての言葉でしょう。しかし、私の叫びというのはそうではないのです。その「石ころ」の意味は、それまで、さいなまれた、踏まれたという、そういう否定的な話をしましたけれども、私の「石ころ」というのはそうではないのです。やはり、踏まれながらも、さいなまれながらも、圧力で押されても、しかし、私たちのこの小石たちは、非常に正しく生きて来た。そういう圧力を忍んで来た。そのように踏まれながらも立派に生きて来たという、そういう考えを持っているのです。
ハイウェイなどは一日に何千台も車で通るでしょう。あの道の生命はどこにあるのですか。見えないその中の数千万の石ころがびっしりと詰められていて、それで、どのような洪水でも壊れないで、そういうしっかりとした道を作るのではないのですか。そういう道の上に舗装をして、それではじめて多くの自動車が安心して走れるのでしょう。それで、石ころとしての一つの生き方の意味を持っている。やはり、世間に対して、人生に対して一つの使命感を持っているし、さっきも言ったような世の中の様々な圧力まで私たちが堪えている。
小鹿島に行ってみなさい。皆さん、足がない人がたくさんいます。朝、教会に行くと皆、杖を持って行く。それで帰る時は杖の林なのです。持って行って、その杖をつきながら出て行くんですけど。目が見えない人がたくさんですから。その杖をつきながら帰るのです。足がないのです。電動車がたくさんあるのですけれども。やっぱり、強制労働で失われた手、足。だから、75歳くらいの平均年齢ですけど、日本時代から数えて80、90歳にもなるのです。その人たちが、もう本当に惨めなのです。私自身も三つの障害を持っています。ハンセン病という障害と目が見えないという視覚障害、そして、手も不自由という三つの障害を持っているのです。本当にそこは人間の廃墟たちが集まっているのです。
しかし、そこで生きながら私は一つの幸福感も感じるのです。私は少年の時に教会に行って祈ったことがあります。子供たちの中で説教を聞きながらこう祈ります。
「神様、私もイエス様のように、本当にこの世の中の一番、貧しい人、気の毒な人たちと一緒に、その人たちのために私も生きるようにしてください。」
考えれば、その祈りがかなっているのです。私は小鹿島に入って、また出て来て、また入って行ったのです。今、家内は半身不随で病院に寝ているのですが、24時間の中でほんの30分か40分くらい、私は彼女の所に行って話をしたり、賛否歌を歌ってあげたり、ハーモニカを吹いてあげたり、お祈りをしてあげるのです。すると、彼女は帰る時に、私の手を離さないのですね。それで、看護婦さんが「手を離してあげた方がいいのよ」と言ってくれたりします。私は最後にいつも彼女と別れる時にキスをしてあげます。それは頬ではなく額にしてあげるのです。彼女は非常に保守的な考え方で、恥かしがりやなんです。ですから、もしキスをしましょうと言っても頬にでもしようとしたら大変なのです。韓国語で「ワイカノ」と言うのですが、何するの?とでも言うのですが、「ワイカノ!」と言いながら私を押してひっくり返すかのようにするのです、彼女の手には力があるんですね。それで、私は額にキスをするのです。そうすると彼女は喜ぶんです。あるボランティアに来た女子学生がその場面を見て泣いたというのですね。夫婦というのは若い時の恋愛は本当の恋愛ではなく、結婚の後で本当の恋愛ができるのではないかと私は思っています。毎日、30分くらい、私は恋人の額にキスをしに行くんですけど。
とにかく、私はそういう人たちの間に、そういう廃墟の中で、その人たちと一緒に人生を歩んでいるという、それはまさに私の少年の時からの祈りを神様がかなえてくださったのだと思っています。本当は賀川豊彦さんの本をたくさん読みましたけれども、あの人はなかなか貧しい人たちのために働いた人なのですけれども、私もそういう祈りをしたのですね。トルストイを読みながら、破戒を読みながら、やっぱり、自分が民族のために貧しい人たちの中で生涯を捧げて生きて行けるようにさせてくださいという、そういう少年の時の祈りがかなえられている。だから、私は時々、「あぁ、ありがたいな」と思ったりします。
その意味で、「石ころの叫び」ですが、それは悲鳴ではないのです。それはデモなんかで言う政治的な絶叫でもない。それは石ころの祈り、石ころの讃美、そういう意味がこの言葉には込められているのです。私は15歳の時に阿蘇山に行きました。バスの車掌さんが美しい声で説明をしてくれました。草千里、数百の馬が草をはんでいる。そういう平和な光景を見ながら、あぁ、本当に平和だなと思いました。しかし、頂上に上がってみると全然違うのです。ぼうぼうとした煙があがっている。その下は炎でしょう。それを見て、私は阿蘇山が持っている外面的な姿、平和な姿、その美しい姿。その中にある炎、その両面的なものを持っている、それがキリストの姿なのではないかと思いました。本当はキリストはやさしい人でしょう。愛の人でしょう。しかし、彼の心の中には全人類に対する愛の炎が燃えていたのです。それが十字架で爆発したのですけれども。やはり、私たちの生き方、私の生き方も、そのような火山的なもの。やはり、優しい、平和な姿の一方で、その心の中には人類に対する深い愛とか、皆さんに対する強い愛情を持つべきではないか、これがクリスチャンの一つの姿であり、また、私が生涯の目的とするべき姿ではないかと思うのです。
これから私の人生がどこまで続くかわかりませんけれども、まぁ、2、3年くらいでしょう。できれば、家内を先に行かせて、それで私が後を追ったらいいと思っています。それが1年かかるか何年かかるかわかりませんけれども、やはり、様々な圧力、災難、蔑み、とにかく自分の素性を表わすことができない、そういう人生を生きているとしても、私の心の中には神に対する愛がこのように燃えることができればと祈っています。
長い話をしましたけれども、今晩、私をここに立たせてくださって、非常に恥かしく思う半面、本当に私の人生の夕焼けですね、落照ですね。今晩のこの催しを通して私の落照をもっと美しいものにしてくださったという感じがしています。昔、学生時代に徳富蘆花の文章を読んだことがあります。兄は徳富蘇峰でしょう。徳富蘆花の文章の中で、やはり落照のことについて記した文章がありました。この落照、夕焼けに沈んで行くとしたら、私が生涯、このような催しで、このような光栄極まる場所に立つことはなかなかなかったのですけれども、皆さん、私の生涯を美しくしてくださって本当にありがとうございます。皆さんのご幸福をお祈りします。
最後に、私の最後の言葉として、平和のために尽くしてくれたマッカーサーについて私は思っています。マッカーサーが最後に演説をした時に言った有名な言葉があります。「老兵は死なず。ただ去り行くのみ。」私の今晩の最後のお礼として、老兵は死にません。ただ皆さんの前から去って行くだけですという、その言葉を私の最後のお礼としての言葉にかえさせていただきます。皆さん、ありがとうございました。