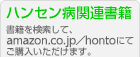韓国定着村とエンマ・フライジンガー女史
―カトリックにおける救らい事業―
現在、大邱市にある「カトリック皮膚科医院」の院長、エンマ・フライジンガー女史は来韓以来30年間、韓国の救らい事業ひとすじに働いて来ている。1990年の夏キャンプの折、慶尚北道にある信愛農場の方から「村の手前に流れている川に橋を架けたり、また定着村での養鶏・畜産経営のやり方などを伝えてくれた人だ」と紹介されたのですが、その他にも彼女の横顔には、まだいくつもの略歴があるようでした。「カトリック皮膚科医院25年史」からエンマ女史の果たした役割と病院のたどった歩みを簡単にまとめてみたいと思います。
過去、日帝統治時代において、韓国のハンセン氏病患者は日本における管理政策と同様に強制隔離を強いられて来ましたが、日本敗戦後、祖国の解放とともに、その状態がそのまま改善の方向に向かったわけではありませんでした。それというのも、解放後に相次いだ社会的な混乱、そして朝鮮戦争での国土の壊滅的な破壊を経験する中で、以前よりももっと悲惨な日常生活を送らなければならなかったのが実情だったからです。戦災から明けた1950年代の後半、このような窮乏状態を目のあたりにしていた当時のカトリック大邱教区の大主教、ソ・ジョンギル氏は、教区長を勤めていたルディ神父(オーストリア人)に担当を依頼し、天主教(カトリック)大邱教区に「救らい事業部」を設立、教護活動を始めた。これが現在、韓国における戦後復興の中でのカトリックの救らい事業の発端だったと言われています。
ルディ神父は、まず本国の慈善事業団体である「カトリック婦人会」へ財政支援を要請し、この資金的な柱をもって救らい事業を進めるための礎としました。そして、最初に行なった仕事というのが、大邱市近郊の高霊郡と義城郡に土地を手に入れ、それぞれに二つの定着場(ウニャン園、シルラク園)を設けたことでした。この当時の状況では、患者さんたちを治療することも大切でしたが、それ以上に、まずは最低限の「衣食住」の支援を行なうことが緊迫した問題として上げられていたので、治療活動とともに、物質的な「救護活動」もまた同時に展開しなければなりませんでした。そして、こうした作業の中で患者さんたちの治療のために看護をする人材の確保も目下の急務とされてきました。エンマ女史が、初めて韓国にやって、この地に足を踏み入れたのは、こうした状況の中ででした。
1932年、12月17日、オーストリア・ザルツブルグ市近郊の町イネブスオプで、建築家の父ヨハン・フライジンガー氏の8人兄弟の2番目の子として生まれた彼女は、1961年の春、ザルツブルグ看護大学を卒業後、道立病院の外科看護院で働いていました。彼女がその後、30年にわたり韓国の救らい事業に携わるようになる、その最初の契機になったのは、この時、ルディ神父と出会い、韓国のハンセン氏病患者の現状を直接に聞いた事が理由とされています。その後、1961年4月24日、先のソ・ジョンギル氏の招請を受けて渡韓。当時、29歳でした。そして、まず最初に向かった土地が、慶尚北道にある高霊ウニャン園。この定着場で患者さんたちと寝食を共にしながら診療活動を始め、その後の病院設立に至るまでの間、約4年間を彼女はここで過ごすことになります。
当時、定着場での巡回診療は、主に近隣の慶北医大付属病院からの助けに頼っていたのですが、時が流れるとともに、たくさんの経験を経るようになり、またそれと共に数々の問題点も現れ出したため、本格的な入院治療を受けられるような現代式の病院を、やはり建設する必要があるという要望が語られ始めました。この時には、既に1961年8月にオーストリア・カトリック婦人会の援助で、大邱市内に看護センターが設立されており、病院建設のための青写真は、その経験を基にして練り出されることになりました。
現在、エンマ女史が院長を勤めている大邱市の「カトリック皮膚科医院」は、この時、1962年に設立されたものですが、設立当時はまさに困難の連続だったと言われています。土地は確保したものの、地元の漆谷(チルゴク)住民の激しい拒絶と反対運動にあい、カトリック関係者らが説得、地方官が仲裁する中で、結局、病院周囲に「塀」をめぐらして患者を外に出さないようにするという条件付きで建設合意。また、当時の政府の財政事情は大変厳しい状態だったため、病院設立へ向けた費用から、その後の運営費、人件費、果ては治療代、薬代に至るまで、その全ての資金をオーストリア・カトリック婦人会からの海外援助に頼らざるをえないという状態でした。また、治療活動と並ぶ救護活動の面でも、小麦粉、古着などの物資を受けていました。創設期の頃は、ここは病院とは言っても、その体裁をほとんど整えておらず、ハンセン氏病患者たちを保護するための収容施設と呼んだ方が適切なほどの有様だったといわれています。
1963年、渡韓以来、高霊ウニャン園において、ずっと診療活動を続けていたエンマ女史が、病院設立を契機として病室管理の仕事に携わるために漆谷にやって来ました。この当時は、ウニャン園、シルラク園、そして漆谷病院の巡回診療は、まだ慶北医大付属病院と大邱カトリック看護協会からの手助けを募っていましたが、1965年に病院本館が建設され、ルディ神父が初代の院長として就任する頃になってからは、創設当初の混乱状態を過ぎ、医療活動もなんとか軌道に乗ったと言える段階に入って行きました。ただ地域住民との間には、その後も根強い軋轢が残っていました。この頃、エンマ女史の発案によって始められた「無料診療」の実施も、当初は住民たちの激しい対立感情を少しでも緩和することが、その理由の一つとしてありました。また、それは一般外来患者の診療を通してハンセン氏病の初期発見に努めようとしていた病院側の姿勢でもありました。
1966年2月、エンマ女史が2代目の院長に就任。この頃、ハンセン氏病患者の初期発見、そして再発検査のための「外来診療」や、車を使った広範囲な「移動診療」が本格的に開始されました。以後、1968年には、それ以前の漆谷病院から、さらに現在のカトリック皮膚科医院へと医療規模も拡大され、1970年12月には、保健社会部長官から感謝杯を授与。1971年7月に、韓国カトリック救らい事業連合会の会長に就任しました。
これらに加え、エンマ女史については、さらにもう一つ、「韓国救らい事業の根本的な転換点をなした」と評されている仕事があります。それは「定着村自活化対策3ヶ年計画」の立案、運営です。その当時、過去15年の間に、韓国の救らい事業に対しては、莫大な規模の外国援助がなされて来たのですが、それらのうちで、今日に至るまでの間に、これという満足の行く成果を実らせたものはまずありませんでした。「今まで、少しずつ努力してきたのに、手伝ってあげていただけで、『生活が苦しい』という声は、いっこうに解消されなかった。」と彼女は言います。そして、今までの無計画で、非生産的な支援のやり方を反省し、定着村の完全自活化による多角的、集中的な支援の方法を再計画し出しました。このようにして1973年、定着村自活化対策のための3ヶ年計画が立案されました。その骨子をみると、まず初年度に、カトリック傘下の約40余りの定着村に対して、環境、開発、産業、労働、指導、地域関係についての実態調査を実施。その後の2年間で、実態に合った事業を集中支援し、完全な自立のための基盤を作るというものでした。そして、この事業に使われるあらゆる財政的支援は、エンマ女史がその韓国支部長を勤めている西ドイツ救らい協会から出されることになっていました。また、彼女自身もこの時にはヨーロッパ中を駆けめぐり、支援を訴えて回ったといわれています。そして現在、この事業の推進が、今日までに至る韓国の定着村自立化政策の一つの契機ともなった出来事として記されています。
エンマ女史は、現在も大邱市のカトリック皮膚科医院の院長として働き、救らい事業に献身しています。その精力的な仕事ぶりは今も変わりません。今日までの間、彼女の仕事を精神的に支えて来たものとは何であろうか?「人間が共同的な社会生活を営む間には、いろいろな原因で暗い影がついてしまうという事は必然的な現状ですが、この暗い現状を少しでもなくそうと、一緒に努力したり助け合ったりすることが、愛を持っている人間の本質ではないのですか?」と彼女は言いました。
1988年、病院設立「25年史」の本の中で、彼女はこう綴っています。「今まで、あまりにも多くの人たちが苦難と試練を経験して来ました。このような心の傷の痛みは癒されなければならないし、新しい患者の方々も、これからは間違った観念から生じる悲惨な苦痛を被ることが二度とないようにしなければならない。」そして、「完治したハンセン氏病快復者は、既に患者ではないのですが、天刑病のような間違った観念に染まった社会が、この人たちを受け入れようとしない」と。彼女は今、「何よりも、社会と定着村とを繋ぐ『架け橋』がほしい」と語っている。
[菊池義弘、1991年5月]